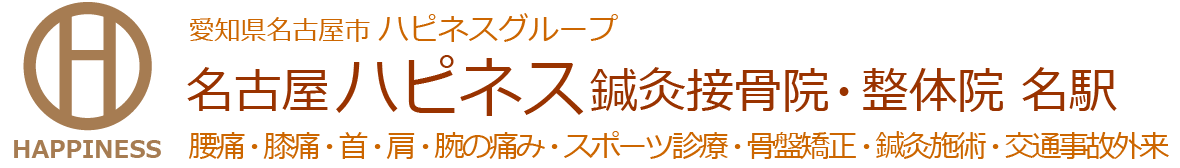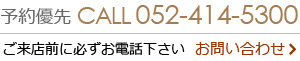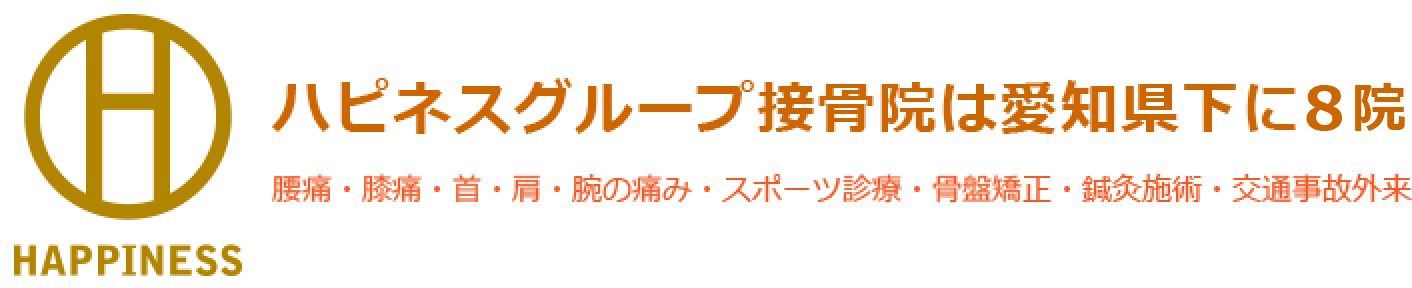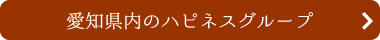みなさんこんにちは!
名古屋ハピネス鍼灸接骨院名駅の藤田です。
2022カタールW杯が昨日終わりましたが、とても盛り上がった大会になりましたね!
日本は死の組に入りグループリーグ突破は厳しいと言われていた中でドイツとスペインに勝利し逆境に立ち向かって結果を出す姿にとても感動しました。惜しくもクロアチアに負けてしまい日本代表史上初のベスト8進出はなりませんでしたが、全世界に日本のサッカーのレベルが上がっていることが証明できたと思います。
勇敢に戦って下さった日本代表に感謝です!4年後も楽しみですね!
さて、今回は「アキレス腱炎」についてです。
アキレス腱炎とは、ふくらはぎの筋肉と踵の骨を結ぶ太くて丈夫な腱であるアキレス腱に炎症を起こした状態のことを指します。
アキレス腱炎はスポーツ選手に多くみられ、剣道や陸上、ジャンプスポーツをする人に発症しやすいと言われています。
地面を蹴ってつま先立ちになる動きが関係しており、運動で繰り返し負荷がかかった後に十分な回復期間をとらないとアキレス腱の炎症が起こります。
主な症状は運動をしているときや座っていて歩き始めるときに、ふくらはぎからかかとのあたりにかけて痛みを感じます。
他にも、アキレス腱を触ると、痛みを感じたり腫れていることがあります。
治療法は安静にして過度な運動を中止し、アイシングと消炎鎮痛剤を服用する保存療法を行うのが一般的ですが、さらに回復を早めるため当院では高周波を用いた電気治療を施します。
高周波は身体の深部にまで電気を届かせることにより高い鎮痛効果を得ることができ、消炎効果もある優れた電気治療器です。
電気というと怖いイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、基本的に痛みはなく患者様の反応に合わせて施術するのでご安心して施術を受けていただくことができます。
ふくらはぎからかかとにかけて痛みを感じる方、少し腫れて違和感を感じる方は是非当院までご相談ください。
名古屋ハピネス鍼灸接骨院・整体院 名駅
TEL052-414-5300
名古屋ハピネス鍼灸接骨院名駅 | 肩こり 腰痛 原因から治療する | 名古屋市 接骨院・整体院